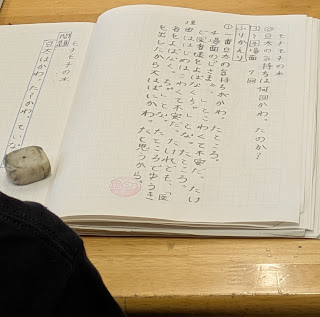いかの変わり揚げ、かぶの浅漬け、五目汁、牛乳、
そして
キムタクご飯でした。
長野県塩尻市の学校の栄養士さんが、家庭料理を
もとにして生み出した給食メニューだそうです。
白菜のキムチとつぼ漬けのたくあん(沢庵)等を
炒めてあたたかいご飯に混ぜ込みます。
(正しくは「キムたく(キム沢)ご飯」なのでは?)
農林水産省のHPの「ふるさと給食自慢」の
コーナーにも取り上げられています。
農水省のこのコーナーでは「あんもち雑煮」や
「福来みかんラーメン」等が
取り上げられていますが、衝撃的なのは
富山県射水市で小学6年生1人1人に提供される
「圧巻の丸ごと一匹ベニズワイガニ給食」です。
射水市の小学校を卒業した子どもたちの
思い出に残る給食第1位なのではないかと…。
来月は、七小の6年生の思い出に残った給食が
続々と登場します。